こんにちは。つきりんです。
前回の記事では、50代からの人生をより自分らしく、充実して生きるためのヒントとして、「やりたいことリスト」の作成法をご紹介しました。
今回は、そこからもう一歩踏み込み、「私はこれから、どう生きたいのだろう?」という“内なる問い” に向き合いながら、心理学の知見と私自身の体験をもとに、「自分を深く知るためのヒント」をお届けします。
以下の3点から、具体的な実践法を交えてご紹介します。
・なぜアラフィフから「自分を知ること」が大切なのか
・心理学が示す「自己認識(セルフアウェアネス)」の効果
・つきりんが実践している「自分を知る習慣」2選
⚠️この記事は、公認心理師としての知識と私自身の体験をもとに情報提供を目的としたものであり、専門的な医療や治療を提供するものではありません。心身の不調を感じる場合は、必ず医師や専門家にご相談ください。
※つきりんに関する略歴や活動の情報は「運営者情報ページ」をご参照ください。
アラフィフから見直す「自分らしい生き方」とは?
アラフィフの世代は、「これからの人生をどう生きたいか」をあらためて見つめ直す、大きな転機の時期とされています。
「これから先、どう生きていこう?」そんな問いがふと心に浮かぶことはありませんか?
実はこのような問いかけは、心理学的にも自然な心の変化とされています。
心理学者カール・ユングは、人の人生を太陽の動きにたとえて、「人生には4つの時期がある」と説明しました。
・少年期・成人前期:太陽が昇る「午前中」
・中年期・老年期:夕陽に向かう「午後」
この中で、アラフィフはまさに「正午」、つまり転換点にあたるとされます。

社会的な役割や評価を重視して生きてきた前半の時間を経て、後半に差し掛かると『本当に自分らしく生きたい』という思いが強くなっていくと言われています。
ユングはこの時期を「人生の正午」と呼び、価値観や生き方を見直すための大切なタイミングであると捉えました。
この「正午」という時期は、決して「不安な変化」ではありません。むしろ『自分らしい人生を歩むための入り口』と言えるでしょう。
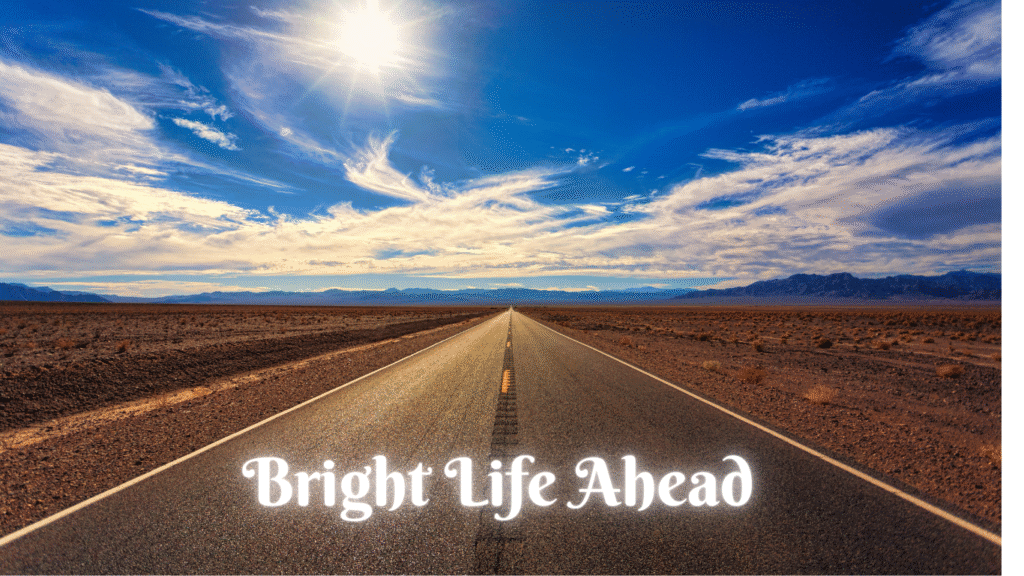
つきりん自身もこの考え方に出会ってから、日々の中で心の声に耳を傾け、自分との対話の時間を意識的に持つようになりました。そして、その時間を通して、自分を知ることの大切さをあらためて実感しました
アラフィフ女性が自分らしい生き方を取り戻すカギは「自己認識」
①自己認識とは何か?
心理学では、自分の感情、思考、行動パターン、価値観、信念など、内面の状態を深く理解することを「自己認識(セルフアウェアネス)」と言います。
WHO(世界保健機関) では、「自己認識(セルフアウェアネス)」を以下のように定義しています:
自分自身、自分の性格、自分の長所と弱点、したいことや嫌いなことを知ること
たとえば、「なんだか気持ちが晴れないな」と感じた時に、「もしかして昨日の出来事が影響しているのかもしれない」と自分の感情の背景を探る。これも立派な自己認識の1つです。
②「自己認識(セルフアウェアネス)」がもたらす心理的メリット
「自己認識(セルフアウェアネス)」は、心理学の中でも注目されている、個人の内面理解に関する重要な概念です。自己認識がもたらすとされる主な心理的メリットには以下のようなものがあります(※効果には個人差があります):
・不安やストレスに対処しやすくなる
・感情のコントロール力が高まる
・自己成長につながる
・共感力が高まり、より良い人間関係が築ける
・自信が高まる
・意思決定の質が向上する
(参考:Courtney E. Ackerman, ALVARADO PARKWAY INSTITUTE)
また、ポジティブ心理学の研究では、自己認識を通じて「セルフコンパッション(自分に対する思いやり)」が育まれることが示唆されています。自分の弱さや未熟さを受け入れ、優しく接することが、幸福感の向上やストレス軽減に寄与するとされています。(参考: 日本心理学会ほか)

つきりんにとって、自己認識の力は、人生後半をより穏やかに、自分らしく歩むための心の支えとなっています。
心がラクになる!自己認識を高める2つの習慣
そこで、つきりんが日々取り入れている『自分を知るための方法』を2つご紹介します。これらは、日々の暮らしに無理なく取り入れられ、前向きな気づきにつながる実践法です。
①毎日の小さな感情に気づく習慣
感情が動いた時こそ、自分を知る絶好のタイミングです。つきりんは以下のような問いかけを日常的に行なっています:
・「どうして楽しかったのかな?」
・「どうして今、嬉しいと感じるの?」
・「なぜそんなにイライラを感じているの?」
・「この悲しさはどこから来てるの?」
・「どうして今、モヤモヤしているの?」
最初はうまく答えが出ないこともあります。それでもつきりんは、問いかけを繰り返すことで、自分の価値観や思い込み、自分の感情傾向や思考の癖などが少しずつ見えてきました。
つきりんはこの“気づき”を手帳に書き留めています。定期的に見返すことで、「自分が大切にしているもの」「どんな傾向があるのか」「反応しやすいポイント」などが整理され、自分軸が育っていきました。
②ノートに書いて心を整える「見える化習慣」
無人島に持っていく物を選ぶというシンプルなワークを通じて、自分の価値観を明確にする方法をご紹介します。このワークは、心理学の価値観探索ワークをアレンジしたシンプルで楽しい方法です。

無人島ワークの手順:
①これから10日間、無人島で過ごすとしたら持っていきたい物を10個書き出してください。
②その10個の中から7個に絞り、書き出してください。
③さらに5個に絞り、書き出してください。
④最後に「なぜそれを選んだのか」「なぜ他の物を選ばなかったのか」、その理由を丁寧に掘り下げてみてください。
例えば、つきりんが選んだ5つのアイテム:
・「アロマキャンドル」
・「チャッカマン」
・「赤ワインボトル1本」
・「マカダミアナッツチョコレート」
・「ふわふわな寝袋」
選んだ理由は、「心を落ち着かせ、気持ちを豊かにしてくれるもの」だったからです。このワークを通じて、つきりんは「安心感」や「感性の豊かさ」が、自分にとって大切な価値観であることに気づきました。
それからというもの、日常でも「本当に大切なこと」にエネルギーを使えるようになり、お金の使い方にも変化が生まれました。
このように、「自分を知る」ことは、日常の中に少しずつ取り入れることができます。自分への問いかけは、心地よい人生後半のヒントをくれるはずです。
アラフィフ世代が「本当の自分」を見つけるヒント
アラフィフはこれまで頑張ってきた自分をいたわりながら、これからの人生をより自分らしく過ごす準備を始める時期とも言えます。
その第一歩が、「自分を知ること」であると、私は感じています。

つきりんも、自分と向き合う時間を通じて、少しずつ「自分に優しくなる」ことができ、日々の満足感が増しています。つきりん自身、自己認識を深める習慣が、日々の小さな満足感や穏やかな心を育ててくれていると実感しています。
まとめ|私らしい生き方は小さな習慣から
アラフィフから始める「自分との対話」は、より自由に、より心地よく生きるための “小さな贈り物” になるかもしれません。
みなさんの「心を満たす5つのモノ」は何ですか?
ぜひノートに書き出して、自分との優しい対話を始めてみてくださいね。
→忙しい日々の中でも「私時間」を作るコツを知りたい方、こちらの記事もおすすめです。
そして、心の声に耳を傾けるだけでなく、体の声にも意識を向けてみませんか?共同著者のケロロが「自分の体の声に耳を傾ける方法」について、日常に取り入れやすい視点でご紹介しています。ご自身をより深く理解するヒントとして、ぜひあわせてご覧ください。
「人生の午後」を、焦らず、自分らしく、そして楽しみながら過ごしていきましょう。
参考にした研究・公的情報
本記事の内容は、私の体験に加えて、以下の心理学の研究や公的機関の情報を参考にしています。気になる方はぜひチェックしてみてください。
・山中康裕,1996, 臨床ユング心理学入門、第1版第1刷,PHP
・マンドフル・セルフ・コンパッション ジャパン(MSC Japan)
☞ホームページを読む

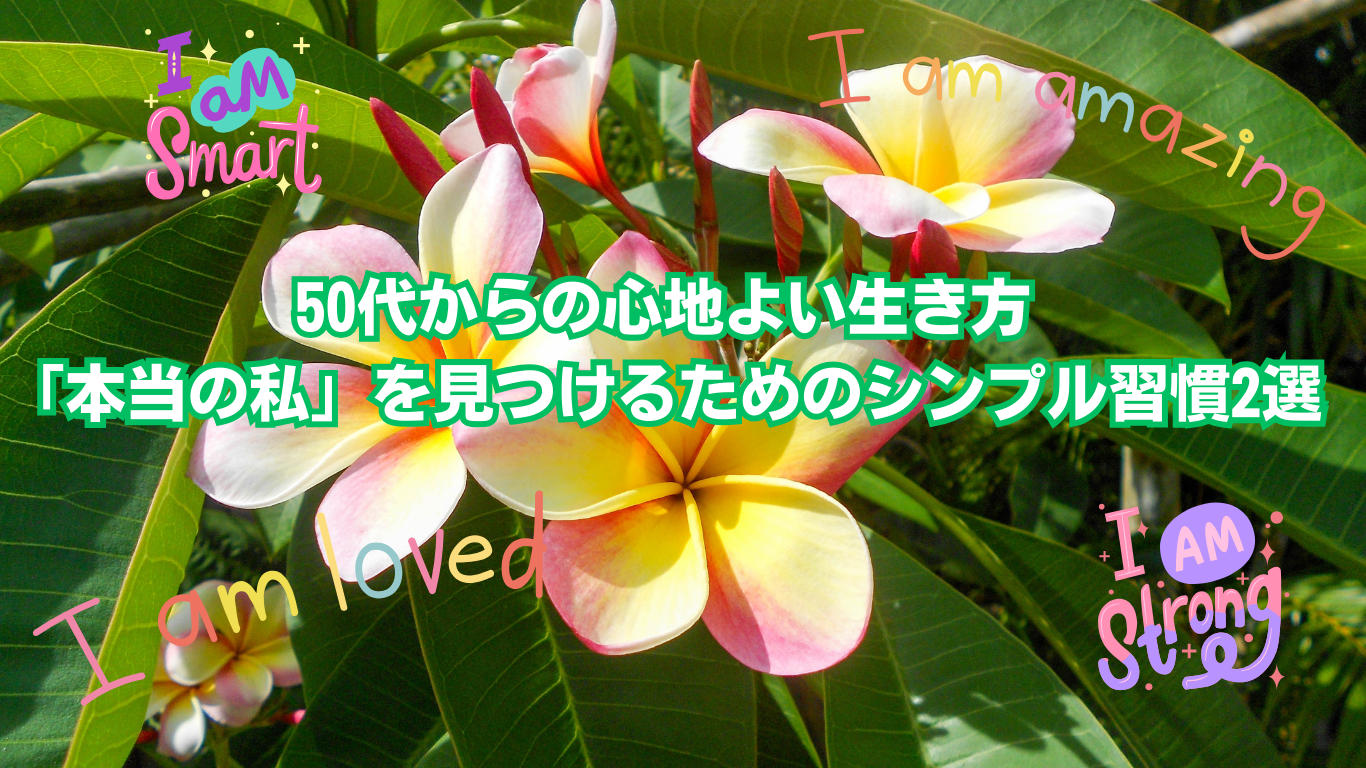
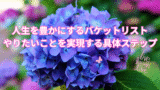


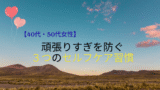
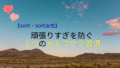
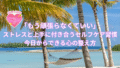
コメント