こんにちは、ケロロです。
長く仕事をしてきた中で「気づかないうちに頑張りすぎて、心身に不調をきたした」経験があります。
頑張ること自体は悪くないのですが、自分の限界に気づけなかったことが大きな反省点でした。
この記事では、ケロロ自身が実践している「頑張りすぎを防ぐ3つの方法」をご紹介します。同じように、無理をしがちな40代・50代女性の方に、少しでもヒントになれば嬉しいです。
※本記事は一般的なセルフケアの提案であり、医療的なアドバイスではありません。体調に不安がある場合は、専門家へご相談ください。
頑張りすぎに気付くための第一歩

呼吸を意識し、自分の状態を知る
頑張り屋さんの多くは「自分が頑張りすぎている」ことに気づきにくいものです。そんな時に役立つのが呼吸への意識です。
呼吸は、自律神経や感情の変化と深く関わっています。
本間生夫教授によると、特に「不安」や強いストレスが続くと、呼吸が早く・浅くなり、呼吸筋の緊張にも影響を及ぼすとされていました(参考:ヘルシスト274号)。
ケロロ自身も、不安やプレッシャーが強いときには呼吸が浅くなっていたのに、そのことに気づかず「大丈夫」と無理をしていました。
今振り返ると、呼吸の変化に早く気づけていれば、もっとい自分を労わる行動(上司に相談する、誰か頼るなど)ができたのではないかと思います。
呼吸の浅さを自覚することは、心と体の声を聴く第一歩です。

ケロロが取り入れているセルフケア習慣
頑張りすぎないためには「日常の中で自分をケアする習慣」を持つことが大切です。
ケロロが続けているのは、次の2点です。
①ヨガと寝る前の深呼吸
②五感を意識する時間を持つ
①ヨガと寝る前の深呼吸

ヨガは呼吸を意識しながら行うエクササイズです。
ケロロはYouTubeの動画を見ながら取り組んでいますが、心配事があると先生のリズムに合わせられず、呼吸も浅くなりがち。そんな時に「あ、いま心がざわついているな」と気付けるのです。
また、寝る前には布団の中で深呼吸をしています。
吸うとき:「新鮮な空気が体にいきわたる」イメージ
吐くとき:「体の中の疲れや不要なものが外に出ていく」イメージ
このイメージを持ちながら呼吸すると、自然と心が落ち着いていきます。
しかしながら、心配事があると、気が散ってうまくそのイメージの深呼吸をするのが難しくなるときもあります。そういうときは、「〇〇のことが気になっている」という自分を理解し、「頑張ってたね」「えらいね」など自分をきちんと労ってあげた後、再び深呼吸に集中します。

脳の専門家、加藤俊徳先生も、著者の中で脳の神経活動には酸素が必要不可欠であり、深呼吸は脳に効率よく酸素を届け、気分をリセットする効果があると述べています。(参考:加藤俊徳 『名医が実践する 脳が変わる超・瞑想』(サンマーク出版))
呼吸に意識を向け、また深呼吸を意識的に生活に取り入れることは、自分の状態を把握できるのと同時に、自分へのケアも兼ねているといえるのです。
朝に瞑想を取り入れるのもおすすめです。詳しくはこちらの記事も参考にしてください。
②五感を意識する時間を持つ

悩みごとがあると、食事の味や香りに気づかないまま過ごしてしまうことがあります。そんな時こそ、意識的に五感を使うことが大切です。
例えば:
・食事のときに「香り」「色」「舌触り」を丁寧に味わう
・散歩中に「風の音」「空の色」を意識してみる
脳の専門家の加藤俊徳先生は、悩みがあると意識が一点に固定されがちだが、身体や感覚に意識を向けることで思考を切り替えられると指摘しています。
つまり、悩みに固定されがちな意識を自分の意志で動かすこと、ただ漠然と意識を変えることは難しいので、意識を向ける対象を『自分自身の身体』に設定し、自分の身体と脳を動かすことによって、手に取れない悩みを間接的に動かしたり、消したりすることに繋がるとのことでした。
そして、にっちもさっちもいかない悩みが出てきてからではなく、普段から五感を意識する時間を取ることで、日々のセルフケアにすることをおすすめします。

脳の専門家、加藤俊徳先生は『名医が実践する 脳が変わる超・瞑想』(サンマーク出版)の中で、人間の脳は、周囲の環境から非言語情報を収集し、他者分析に使う「右脳」と、言語操作によって自己分析や自己主張に使う「左脳」とがあり、他人のことばかりに気をとらわれて自分をないがしろにしていると、右脳と左脳のバランスが崩れてしまい、自分と他人との距離がうまく取れなくなったり、自分のやりたいことや言いたいことが分からなくなったりしてしまうとありました。
つまり、普段より五感の感覚を大切にしていると、悩みから距離を置けると同時に、自分自身に意識を向けることもできるため、自分を見失わずに前向きな選択ができるようになります。

まとめ
40代・50代の女性が頑張りすぎを防ぐには、
・呼吸を通して自分の状態を知る
・ヨガや深呼吸を生活に取り入れる
・五感を意識する時間を持つ
この3つがシンプルで効果的な方法です。
深呼吸や五感への集中は、セルフケアであると同時に「自分を大切にする行為」にもなります。
とはいえ、方法は人それぞれ。自分に合ったやり方を少しずつ探してみてください。もし深刻な不調を感じるときは、迷わず専門家の助けを借りることをおすすめします。
今日のあなたが健やかに過ごせますように。
参考にした研究・公的情報
本記事の内容は、私の体験に加えて、以下の研究や公的機関の情報を参考にしています。気になる方は、ぜひチェックしてみて下さい。
・本間生夫 「呼吸筋を鍛えて「良い呼吸」を手に入れよう」
☞ホームページ記事を読む
・加藤俊徳 「名医が実践する 脳が変わる超・瞑想」
☞本を読む

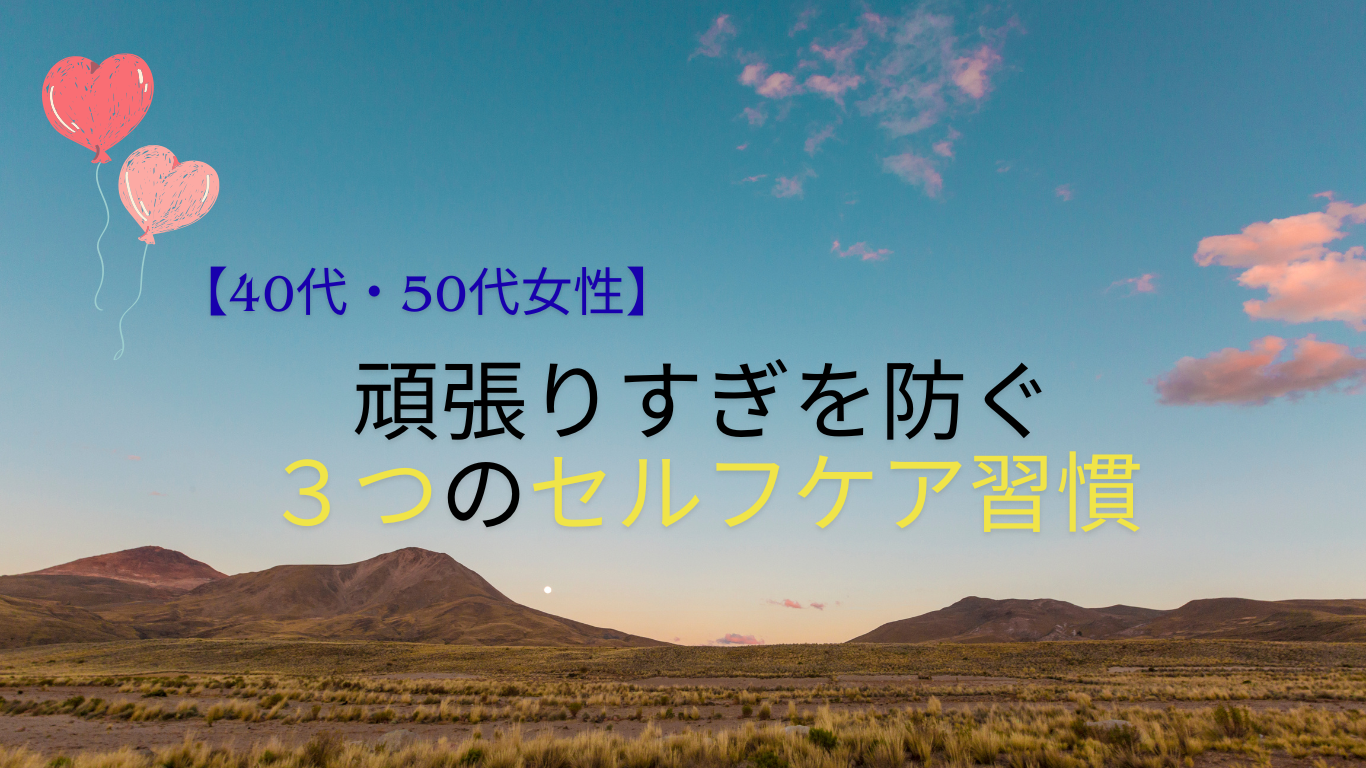
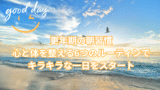
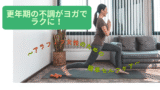
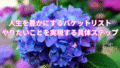
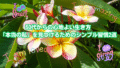
コメント