こんにちは、ケロロです。
アラフィフになると、人との関わりが固定化しやすくなり、価値観も知らず知らずのうちに凝り固まりがち。
でも、世代の違う人とのコミュニケーションは、自分の考え方を柔軟にする最高のチャンスです。
今回は、アラフィフ世代が価値観を広げながら、世代間コミュニケーションを通じて思考をしなやかに育てるヒントを体験談とともに紹介します。
※この記事で紹介する方法は、個人的な実体験をもとにした一般的なアドバイスで、個別の状況に対しては最適ではない可能性があります。健康に関する重要な決定は、専門家の助言を受けて下さい。

アラフィフから人間的な幅を広げるポイント
心理学では、「外部環境からの変化に対して考え方を柔軟に変化させることができる能力」のことを『認知的柔軟性』と呼び、困難な状況からからの回復力や幸福度に役立つと言われています。(参考:産業能率大学 総合研究所)
しかし、年齢とともに考え方が固くなるのは自然なことです。
でも、アラフィフはすでに自分の軸ができている年代。大切なのはその軸を生かしながら、新しい視点や価値観を取り入れることです。
例えば、若い世代の価値観を知ることで、自分の中の「当たり前」が見直され、新しい考え方を柔軟に取り入れやすくなります。
若い頃の順応力には及ばなくても、人生経験を活かして自分の視野を広げることは十分可能です。
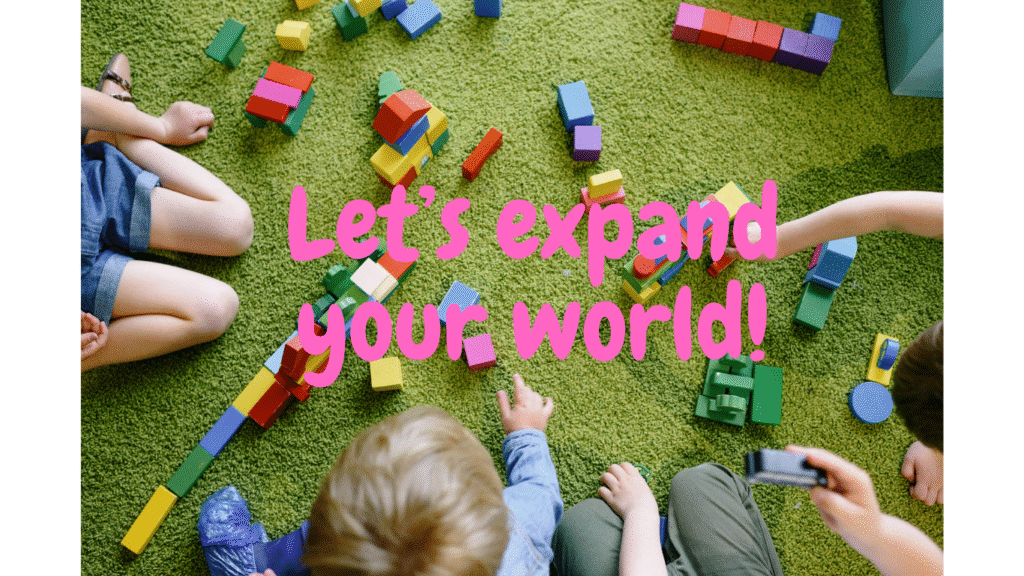
世代の違う人とコミュニケーションを取るメリット
子どもが幼児の頃、アラサー世代のママ友だちと関わることで、アラフォーの私は多くの刺激を受けました。
例えば、ケロロの体験談としては、インスタグラムの使い方やディズニーの攻略法など、自分の世代だけではなかなか得られなかった情報や価値観に触れることができました。
そんなかかわりの中で、次のようなメリットを感じました。
・子育ての悩みを共有できる
・世代による価値観や興味の違いに気づく
・自分が知らなかった情報や習慣を学べる
こうした小さな気づきが、結果的に自分の考え方の幅を広げるきっかけになりました。
違う世代との関わりは、自分の価値観を見直すきっかけになり、人間的な幅を広げるチャンスになります。

世代間コミュニケーションの具体的なコツ
①共通の話題をみつける
共通の話題があると、会話は自然に盛り上がります。
子どもや仕事、趣味、ペット、最近観た映画など、自分が興味を持てるテーマを探すのがポイントです。
例えば、職場ではスクリーンセイバー、公園などではカバンに付いているキーホルダーなどをチェックしてみましょう。そこから話題のきっかけが生まれることもあります。
違う世代の人と話す時も、まずは**「共通点探し」**から始めると、自然に距離が縮まります。

②会話がうまく続かないときの心の持ち方
とはいえ、世代の違う人とコミュニケーションを取るのは、新しい発見がある一方で、少し気を使う場面もあるものです。
うまく会話が続かなくても、「世代が違うからしょうがない」と気楽に受け止めてOK。
「でも、話しかけようとした自分はえらい!」と、自分をちゃんと労わってあげましょう。
こうして少しずつ関わりを重ねるうちに、きっと距離が縮まっていきますよ。

③言葉遣いに気を付ける
丁寧な言葉遣いは、相手も自然い礼儀正しい対応をしてくれるきっかけになります。
心理学では「ミラーリング効果」と呼ばれ、相手の態度や言葉遣いを無意識にまねる傾向があり、自分が丁寧に接することで、相手も自然と同じトーンで応じやすくなるのです。そして、ミラーリング効果は、よい人間関係を築くテクニックとしてよく紹介されます。(参考:立正大学)
ケロロの体験談として、ママ友との間では、年上の私が丁寧な言葉遣いをしていると、大抵年下のママたちも言葉遣いを意識して話してくれると同時に、距離感が縮まりすぎず、適度な関係性を保つことができました。
また、若い人の中でも、自分が年下と判明したとたんに相手の言葉遣いが変わり、不快な思いをしたという話もあります。
**親しさがあっても、「親しき中にも礼儀あり」**を忘れずに意識しましょう。
日常で実践するコツ
世代を超えて交流することで、自分の中の「当たり前」が少しずつほぐれていきます。
相手を理解しようとする姿勢が、自然と柔軟な考え方を育ててくれるのです。
世代間コミュニケーションで広がった価値観を、日常の中で生かすには「行動の習慣化」も大切です。
小さな一歩を続けるコツを知ることで、より柔軟な思考が定着していきます。
まとめ
世代の違う人とのコミュニケーションは、価値観を広げ、思考を柔軟にする絶好のチャンスです。
私の場合、多世代のママたちと繋がることで、共感できる幅や理解力が広がったと感じています。
言葉遣いに気を付ける
共通の話題を見つける
この2つを意識すれば、世代が違っても自然にコミュニケーションを楽しめます。
柔軟な思考を育てたあとは、自分の興味を広げて脳を刺激するのもおすすめです。
新しい視点が増えることで、さらに人との関わりが豊かになります。
参考にした研究・公的情報
本記事の内容は、私の体験に加えて、以下の心理学の研究や公的機関の情報を参考にしています。気になる方はぜひチェックしてみてください。
・産業能率大学 総合研究所 「不確実性の時代を乗り切るスキル ~認知的柔軟性とは~」
☞記事を読む
・立正大学 「心理学とは?学ぶ魅力を徹底解説!」
☞記事を読む

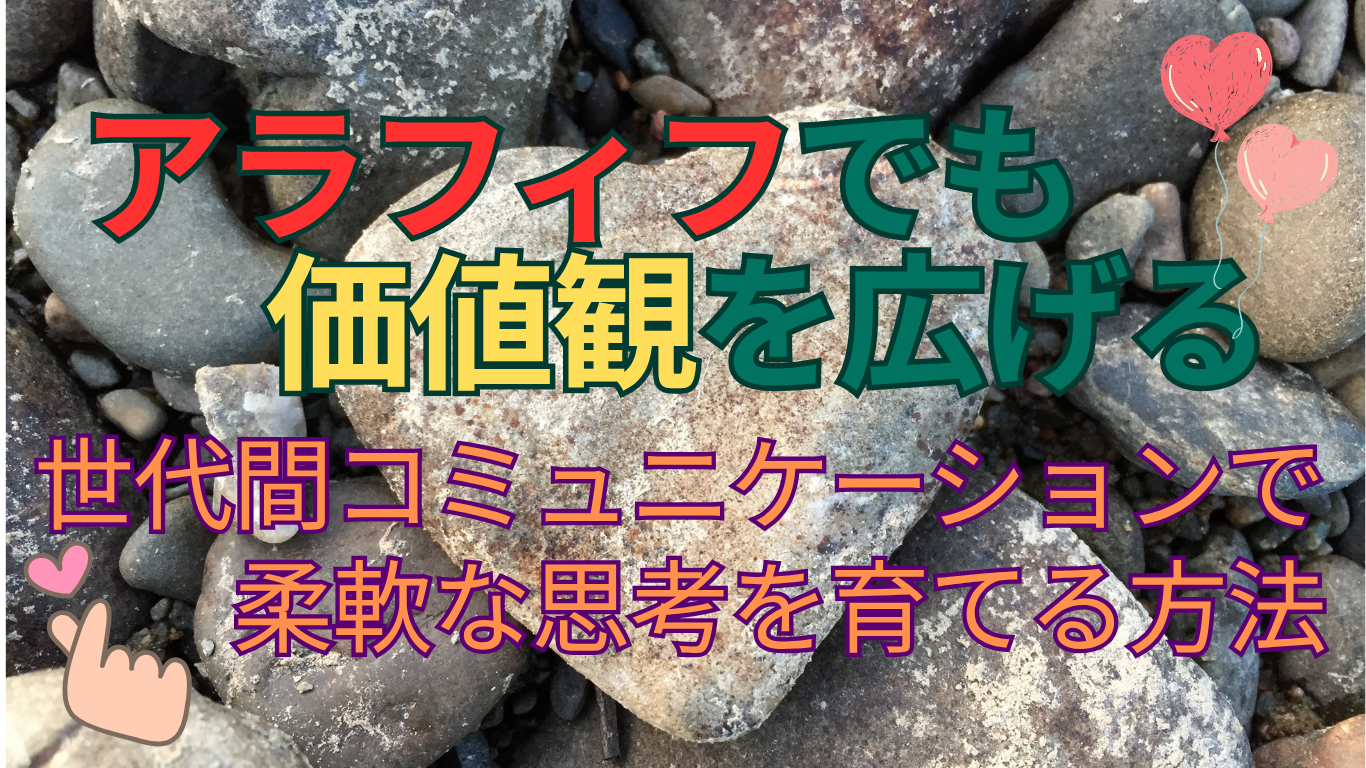

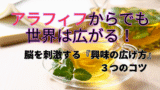

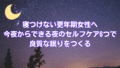
コメント